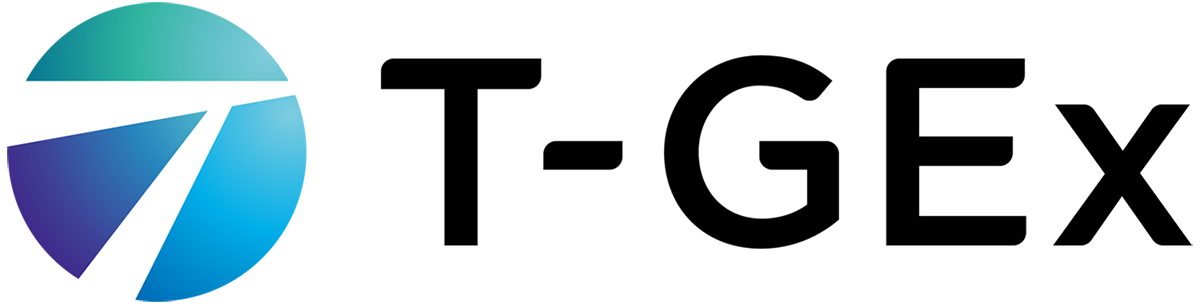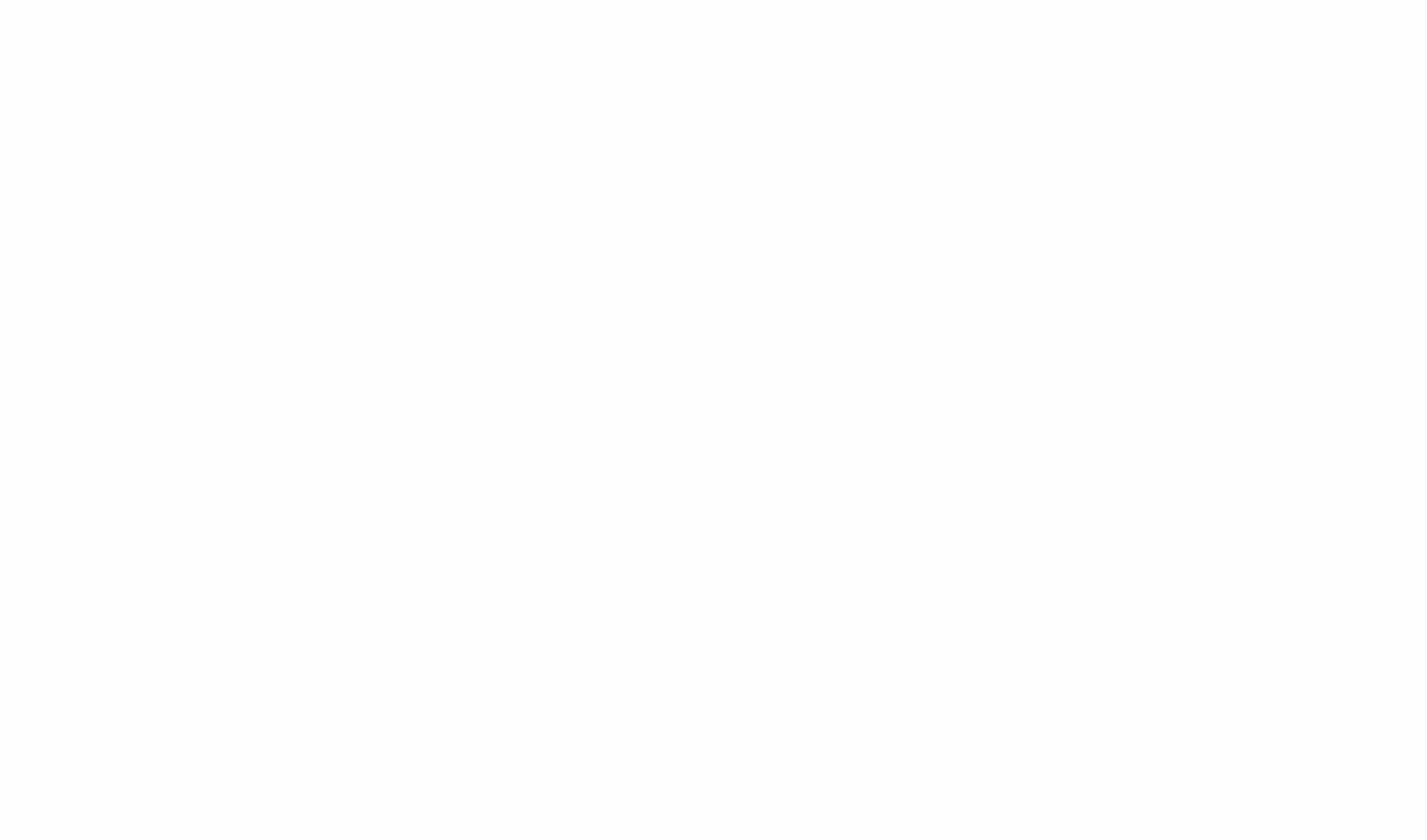このイベントは終了しました。
多くの方にご来場いただき、ありがとうございました。
本事業のT-GExフェロー、アソシエートおよび企業アソシエートが推進している先端研究に関しまして、これまでの研究成果および成果物を発表させていただきます。
幅広い参加者(異なる専門分野の研究者、あるいは研究者以外の方々)に研究の意義をご理解・共感いただくと共に、今後の発展に向けたアドバイスをいただくことを目的としています。
今回の研究成果エキシビションでは、「研究と社会の接点」をテーマに掲げました。研究と教育はこれまで学術の場を中心に発展してきましたが、複雑で多様化する現代社会においては、その営みを社会の広い領域と結びつけ、新たな価値を創出していくことが不可欠です。社会の課題を研究に取り込み、同時に成果を社会へ還元することが、
今まさに強く求められています。
では、未来を切り拓くために、研究は社会とどのように結びつき、共に歩んでいくべきなのでしょうか。本エキシビションは、そうした問いを出発点として企画されました。特別講演では、科学技術社会論の第一人者である東京大学の横山広美先生にご登壇いただき、「研究と社会の接点」を考える上での重要な視座である科学の信頼についてご講演いただく予定です。分野や立場を超えた視点からこそ、新たな気づきが得られるはずです。
本エキシビションが、分野や業種を超えた交流や共同研究の創出につながるだけでなく、学術研究と社会との相互作用を改めて考える機会となれば幸いです。
-
開会のご挨拶
-
加藤 剛志(東海国立大学機構 名古屋大学 教授)
特別講演
-
特別講演
-
ポピュリズム時代の科学信頼
講演者横山 広美 氏(東京大学 教授)

科学の信頼は、科学を実行する科学者の信頼や、データへの信頼などいくつかに分けることができる。Covid-19の後、意外にも科学への信頼は下がらなかったが、世界では気候変動をはじめ深刻な問題も多い。日本においても対岸の火事ではなく、リベラル・保守による科学への信頼には違いがある。当日は科学の信頼や、危機時の科学的助言を「グループボイス」で行うことの利点について紹介する。
ショートプレゼンテーション & ポスター発表
-
ショートプレゼンテーション
-
後のポスター発表の概要を1人1分でお話しいたします。最も優れたショートプレゼンテーション発表者の投票をぜひお願いいたします。
-
休憩
-
ベストプレゼンテーション発表者の投票をぜひお願いいたします。
-
ポスター発表
-
紙ポスターに加え展示品もご覧いただけます。オンサイトならではの深い議論をぜひお楽しみください。
-
休憩
-
全体アンケートへのご回答をぜひお願いいたします。
-
閉会のご挨拶
-
武田 宏子 プログラム・マネージャー (東海国立大学機構 名古屋大学 教授)
開催場所

会場内観
-
2階 FUJIホール(特別講演会場)

-
2階 多目的スペース(ポスター発表会場)

ダウンロード
イベントチラシのダウンロードはこちら

お問い合わせ
T-GEx事務局(名古屋大学内)
t-gex[at]t.mail.nagoya-u.ac.jp
※メール送信の際は[at]を@に置き換えてください。
ポスター発表題目・アブストラクト一覧
| 氏名(所属) | 題目・アブストラクト |
|---|---|
|
髙橋 香苗 名城大学 |
誰が調査に協力するのか私たちが何かを調査、特に人や社会を対象に調査をする場合には、誰かの協力を得なければならないが、どのような人が協力をしてくれ、どうしたら継続した協力関係を築くことができるのだろうか。20年以上に渡って継続するパネル調査の自由回答記述を計量テキスト分析によって検討してみると、①謝礼が存在することが協力当初のモチベーションであるが、②協力した調査のフィードバックがあること、③協力しているという実感がもてることを通じて、④調査に協力することが日常化していることが継続した調査協力につながっていることが明らかになった。一方で、非正規雇用で働いている、病気などで休職をしている時期は協力に消極的になるということもわかった。そのため、少なくとも本人の意識の上で、社会的に「標準」とされるライフコースから逸脱している場合に調査協力を敬遠しやすくなると考えられる。調査に協力するという段階でセレクションバイアスが存在することを改めて認識した上で、被調査者との継続的な協力関係を維持していくことが質の高い調査データの確保につながる。 |
|
星野 藍子 名古屋大学 |
当事者の声を可視化するメンタルヘルス領域の参加型アクションリサーチうつ病をはじめとするメンタルヘルス不調に対しては、これまでさまざまな対策が講じられてきた。しかし、実際に休職を経験した当事者の声がその対策に十分に反映されることは少なく、当事者の経験は長らく不可視化されてきた。その背景には、メンタルヘルス不調に対する根強いスティグマ、雇用者と労働者の間に存在する権力勾配、さらに適切な研究手法の不足がある。本研究では、参加型アクションリサーチの手法を用い、これまで可視化されてこなかった当事者の声を明らかにした。その結果、医療や福祉の枠にとどまらない職場づくりへの示唆を得るとともに、当事者自身のエンパワメントを促すことができた。本発表では、現在進行中のプロジェクトの一部を紹介し、得られた知見の実装可能性について議論したい。 |
|
山内 星子 中部大学 |
高い創造性を発揮する理系研究者への臨床心理学的接近心理学領域では従来、拡散的思考(柔軟性、新規なアイデアを多く生み出す思考)が創造性の主要な要素として位置づけられていた。その結果、実際的な成果を生み出す研究者の認知、人格特性はほとんど解明されてこなかった。しかし近年では、拡散的思考の対概念である収束的思考(複数の可能性やアイデアを評価・分析し、最適解や解決策に絞り込む思考)の重要性や、「本物の成果」、すなわち、その領域の専門家の観点から見て質の高いものが生み出されているか否かによって評価されることが重要という指摘など、創造性の捉え方は変化を遂げつつある。そこで本研究では創造性を“新奇で有用な産物を生成する能力”と定義し、顕著な業績を持つ理系研究者および大学院生を対象に、臨床心理学の専門的手法である心理検査を用いて、創造性を支える特性の記述を試みた。本発表では、結果に基づきグルーピングされた各群の認知的、人格的特徴と専門分野との関連、また、本結果から見える研究者としての発達的変化に関する考察を紹介する。 |
|
森田 尭 中部大学 |
構造化状態空間モデルにおける初頭効果の発生構造化状態空間モデル(Structured State-Space Models; SSM)は、従来のリカレントニューラルネットワーク(RNN)よりも記憶の長期保持を実現しつつ、リアルタイム推論能力を維持し、さらにTransformerにおける時間計算量の制約を克服する次世代AI基盤として期待されている。 本来、SSMの記憶は、理論上時間とともに単調に減衰するよう構築されており、より新しい入力ほど正確に保持されるはずである。 しかしながら、統制された人工的記憶課題を用いてSSMの記憶バイアスを検証したところ、理論上の設計に反し、SSMは主として最初に提示されたデータを重点的に記憶保持する傾向(初頭効果)を示した。 この発見は、SSMに関する現行の理論的理解に新たな課題を突きつけるとともに、今後の研究に新たな方向性を提示するものである。 |
|
奥原 俊 三重大学 |
効用に基づく大規模言語モデルを用いた交渉対話からの合意生成本研究では交渉場面における合意の文章の作成と合意を自動で判定することを目的とし、効用に基づく大規模言語モデル(LLM)による合意を判定する機構を開発する。従来のLLMは自然言語生成に優れているが個々の参加者の効用や選好を明示的に反映することが困難であった。本研究では各AIエージェントの効用を事前に定義し、入力条件としてLLMに与えることで合意形成文章を生成する。さらに生成された合意形成文章を分析し、参加者の効用に基づいて評価する合意判定モジュールを設計する。提案した仕組みにより、自然言語に基づいた意思決定過程が把握可能になることで透明性を高め、説明可能なAIによる合意形成支援の実現を目指す。 |
|
杉原 進哉 天筒 智也 株式会社ネオレックス |
企業におけるAIの活用弊社では「AI委員会」を設置し、社内でのAI活用を推進している。本発表では、その中で行っているいくつかの取り組みを紹介する。具体的には、AIコーディングの試行、社内ドキュメントの活用、議事録自動生成ツールの検証などである。これらの活動を通じて、生成AIを日常業務にどのように実用的に取り入れられるかを探っている。まだ試行段階ではあるが、得られた知見をもとに、今後は社内全体での自発的かつ継続的なAI活用の広がりを目指していく。 |
|
山本 真之 株式会社デンソー |
教育の観点を考慮した配送計画最適化近年、ネットスーパーの需要拡大に伴い、効率的かつ持続可能な配送計画の重要性が高まっている。本発表では、ネットスーパーにおける配送計画最適化手法について報告する。数理最適化技術を活用した配車割当・配送ルート案内により、ピッキング完了時刻を考慮した待機時間の最小化と、配送距離・時間・配達件数等のKPI改善を実現した。さらに、配送ドライバーのスキルに応じたコース割当や、未経験エリアへの段階的な教育を組み込むことで、使うほどにドライバーが成長し、担当エリアを拡大できる仕組みを構築した。24年度に三重県内のネットスーパーにて実証実験を行い、配達件数7%向上、人件費削減、配送時間短縮などの効果を確認した。本手法は配送計画立案の属人化を解消し、ノウハウを標準化することが期待される。 |
|
野崎 佑典 名城大学 |
エッジAIハードウェアに対する回避攻撃の安全性評価AI技術が社会の様々な所で活用されている。一方で、AIの推論を意図的に誤らせる回避攻撃の脅威が報告されている。そのため、安心安全なAIの利活用を推進する上で、これらの脅威に対する評価や対策は重要である。本研究では、エッジAIハードウェアにおける回避攻撃とその安全性評価手法について紹介する。 |
|
岡田 大瑚 岐阜大学 |
ブロックチェーン技術を活用した知識共有システム科学の研究は多くの研究者や研究室の協働によって進められているが、研究の過程で生じる知識やデータの共有・継承・再利用には多くの課題が存在する。特に、論文化されていない知見は失われやすく、共有や再利用が困難である。本研究では、こうした課題を解決するため、研究チーム内で科学的知識や成果を簡便に共有できるWebアプリケーション「Shizui vault」を開発した。本システムでは、成果を最小単位で投稿・記録でき、投稿内容は暗号化されたうえでSYMBOLブロックチェーンに記録される。これにより、投稿内容の存在と日時の証明を可能にし、研究プロセスの透明性と信頼性が向上する。Shizui vaultは、学術研究における小さな発見やアイデアを未来へと継承する、新たな知識共有の基盤である。 |
|
田村 秀希 豊橋技術科学大学 |
VR空間におけるヒト視覚系の物体材質識別ヒト視覚系の物体材質識別メカニズムを明らかにするため、従来の研究では、モニタ上に呈示された物体刺激を一定の距離や角度から観察させ、その材質を判断させるという受動的な心理物理学的手法が用いられてきた。しかし現実世界では、宝石を鑑定する場合のように、私たちは物体をさまざまな角度から観察したり、手に取って動かしたりしながら質感を評価するという能動的な戦略をとる。本研究では、このような能動的観察行動が物体材質の識別にどのように寄与するかを検証するため、VR環境内で観察者が自由に行動しながら物体を観察できる実験系を構築し、その行動的・知覚的特徴を分析した結果を報告する。 |
|
小路 真史 東海光学ホールディングス株式会社 |
文字と乱視軸による読みにくさの評価同じ乱視度数においても乱視軸の違いで視力や読書に影響があることは示唆されているが、読書タスクそのものぼやけ方の違いの影響は検討されていない。情報エントロピーを用いた文字のぼやけ方の定量評価手法を開発した。人工的に作成した乱視眼での読書速度の測定結果と、使用した読書タスクの評価結果を比較し、有意な負の相関があることを示した。 |
|
本田 康平 名古屋大学 |
視覚型自律移動ロボットのための環境の理解と表現ロボットが遠くのゴールまで自律的に移動するためには、環境に関する事前知識が必要である。これは人間も同様で、初めて訪れる場所でも「地図」という事前知識を頼りに目的地へ向かう。本講演では、従来のロボット用地図が抱える課題を整理し、特にカメラを主なセンサとして移動するロボットにとって望ましい環境地図のあり方について、いくつかの研究事例とともに紹介する。 |
|
舟山 啓太 株式会社豊田中央研究所 |
堅牢で機能的な信号伝達を可能にするトポロジカル導波路量子マテリアル中のトポロジーの概念を応用した「トポロジカル絶縁体」は量子・古典的波動現象や拡散現象を制御する新規技術として注目されている。本研究では、トポロジカル絶縁体の特徴である「低損失・高効率な波動伝播」という特性に着目し、トポロジカル絶縁体から成る導波路を信号やエネルギー輸送路として応用することを目指している。しかし、トポロジカル導波路中を伝播する”波”は外乱に対して堅牢であるが、言い換えると能動的な制御性が乏しく、システムとして機能性を付与することが難しいことが課題となっている。本発表では、“波”の周波数によって結合強度が能動的に制御可能なトポロジカル結合素子の開発に成功し、その素子を用いてデジタル通信へ応用した実証結果に関して紹介する。 |
|
東 直輝 名古屋大学 |
マイクロ・ナノ構造を用いた生体分子の操作と分析大分子量DNA分子の分析は、細菌やヒト細胞などを対象とする生物学、疫学、医学における基礎・応用研究の双方で重要である。しかし、大分子量DNA分子は巨大かつ高い柔軟性を有するため、ゲル電気泳動やカラムベース法といった従来手法では、高精度かつ高速な分析が困難となる場合が多い。本研究では、発表者らが開発を進めてきた、流路内に形成されたマイクロ・ナノスケール構造を利用することで、高精度・高速な分析を可能とする手法を紹介する。本手法は、微細構造によって分子の運動や変形を操作することで分析を実現するものであり、DNA分子の物理的特性との関係に基づいて構造や泳動条件を設計することで、分離、濃縮、および一分子分析など、大分子量DNA分子の迅速かつ高精度な解析を実現できる。 |
|
公文 広樹 浜松ホトニクス株式会社 |
超小型パターンレーザを用いたマイクロ流路内の細胞速度計測マイクロ流路は、血液検査をはじめとする細胞分析において不可欠な技術です。特に、マイクロ流路内を流れる細胞の速度を高精度に測定することは、細胞の計測および選別の精度向上に直結します。本研究では、オンチップで任意パターンを生成できるレーザーを作製し、レンズを用いることなくマイクロ流路内に干渉縞を生成することに成功しました。これにより、従来の手法では困難であった高ダイナミックレンジかつ高精度・高確度な細胞速度計測を実現しました。本成果は、細胞解析技術のさらなる高度化に貢献するものと期待されます。 |
|
上野 藍 名古屋大学 |
MEMSウェアラブルデバイスを基盤とした次世代体内モニタリング技術の創出本研究は、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)技術を基盤としたウェアラブルデバイスにより、次世代の体内モニタリング技術を創出することを目的とする。特に、体内の生理的情報を非侵襲的に取得し、鉄欠乏性貧血を早期に検出することを目指している。提案するデバイスは、絆創膏のように皮膚に貼付することができ、汗などの体液中から鉄代謝状態を示すバイオマーカーであるフェリチンを検出する。これにより、従来の採血を必要とする鉄欠乏検査とは異なり、簡便かつ継続的な生体モニタリングを可能にする。本発表では検出精度を向上させるため、新規のデバイスモデルの提案、設計、MEMSデバイスの作製、評価を行ったので、報告する。 |
|
澁谷 拓未 ホーユー株式会社 総合研究所 |
バイオインフォマティクス技術を活用した髪質ごとの特徴分析毛髪はそのカールパターンに基づき「ストレート」「ウェーブ」「カーリー」「コイリー」の4つに分類され、さらに太さや質感などの物性により細分類される。しかし、これらの髪質の違いが分子レベル、特にタンパク質組成にどのように対応しているかは十分に明らかにされていない。 本研究では、毛髪の物性(毛径・引張特性)とプロテオーム解析結果を統合的に解析することで、髪質ごとの構造的・分子的特徴を明らかにすることを目的とした。対象とする毛髪は、日本人、韓国人、トルコ系、ヨーロッパ系、アフリカ系の複数民族にわたり、バイオインフォマティクス技術を用いて、物性とタンパク質発現の関係性を多角的に評価する。 本研究は、髪質の多様性を分子レベルで理解する新たな視点を提供し、将来的な個別化ヘアケア製品の開発や、民族・人種に応じた美容・医療応用の基盤構築に貢献することを目指す。 |
|
平島 一輝 岐阜大学 |
植物二次代謝物と動物代謝の交差がもたらすがん転移制御特定の植物が産生する代謝物の中には、哺乳動物のミトコンドリアに作用してその活性を阻害するものがある。とりわけ、ミトコンドリア複合体 I を阻害する植物代謝物はこれまでに多数報告されてきた。しかし、従来の報告例に含まれる物質の多くは毒性が高く、植物毒として扱われてきたため、医学領域で十分に活用されるには至っていなかった。平島らは、日本原産の食用植物であるフキから新たな特性をもつ植物代謝物ペタシンを同定した。ペタシンは、フキが環境に応じて代謝系を変化させて生成する物質(二次代謝物)であり、強力な複合体 I 阻害活性と抗がん・抗転移効果を示す一方で生体毒性がほとんど認められないという独自の特徴を有している。今回の発表では、植物由来のペタシンが哺乳動物細胞の転移に種を跨いで与える代謝的影響を考察する。 |
|
伊吉 祥平 名古屋大学 |
卵巣癌腹水の大規模プロテオミクス解析による分子型サブグループと予後マーカーの探索卵巣癌は腹水を介して腹腔内に直接播種することが知られ、最も予後の悪い婦人科悪性腫瘍の一つである。腹水中には、癌細胞だけでなく、免疫細胞をはじめとする非腫瘍細胞も多数存在し、これらの細胞からプロテアーゼや、その基質となるサイトカインが放出されることが知られているが、腹水中におけるタンパク分解シグナルの詳細について検討した報告はない。本研究では、高悪性度漿液性卵巣癌(HGSOC)91例から採取した悪性腹水を用いて、データ非依存解析(DIA)法による大規模プロテオーム解析を行い、悪性腹水のプロテオームシグネチャーを評価するとともに、バイオマーカー候補の探索を行った。その結果、3つの異なるサブグループを同定し、各サブグループ間で蛋白分解活性が有意に異なることを確認した。また、CoxBoost法を用いて、予後に関連するバイオマーカー候補を抽出し、得られた分子群のエンリッチメント解析から、凝固・補体活性化が予後と相関することを確認した。これらの結果からプロテオームリソースとしての腹水の有用性が示唆された。 |
|
横井 暁 名古屋大学(病院) |
EV解析による女性のトータルヘルスケア課題解決体液中の細胞外小胞(EVs)は病態に応じてそのプロファイルが変化することが知られており、様々な臨床応用が期待されている。近年、女性の総合的な健康管理課題は劇的に変化しており、本研究ではEVを中核に据えた調査を通じてこれらの課題解決に貢献することを目指す。課題に応じて血液、尿、卵胞液、羊水、癌性腹水など様々な体液を分析し、革新的かつ実用的な医療実現に寄与するエビデンスの蓄積を図る。 |
|
由良 義充 名古屋大学(病院) |
クローン性造血;心血管病を促進する隠れた機構心血管病は世界の先進国で最大の死因であり、全死因の約30%を占める。高血圧や脂質異常などの冠動脈疾患のリスク因子を十分に管理しても冠動脈疾患や心不全の予防・治療に難渋する例が多いことから、未知の因子が関与している可能性が示唆されていた。そして近年、加齢と共に骨髄で起きる「クローン性造血」という現象が、心血管病の独立した危険因子であることが報告され、心血管病の病因解明における重要な新知見として大きな注目を集めている。 造血幹細胞は自己複製と分化を繰り返し、生涯にわたって全身に血液細胞を供給し、生体の恒常性維持の根幹を担う。細胞が複製する際には一定の確率で遺伝子変異(体細胞変異)が起き、加齢とともに変異を有する造血幹細胞(クローン)が骨髄内で増殖する「クローン性造血」と呼ばれる現象が起きる。遺伝子変異は末梢免疫細胞にも引き継がれ、この変異免疫細胞が血管や心臓に浸潤して、組織傷害を起こし動脈硬化・心機能障害を助長するという全く新しい心血管病のメカニズムが提唱されている。 本エクシビションでは、クローン性造血と心血管病に関する疫学的な報告を紹介した後、加齢やがん治療に伴って助長されるクローン性造血が心血管病を引き起こす機構について、動物実験の結果を中心に概説する。この分野の研究の現状を把握し、今後クローン性造血に着目した新しい診断・治療を実現させるために解決すべき課題について討議する場となれば幸いである。 |
|
新谷 正嶺 中部大学 |
心筋サルコメアの周期的カオス恒常性心筋の拍動はサルコメアの周期的短縮から生じる。本研究は、温度刺激下(37–42℃)の単離心筋細胞で、サルコメアがCa変動と独立に自律振動し、振幅・位相は不規則に揺らぐ一方、細胞全体の拍動は保たれ、各サルコメアの周期はほぼ一定(CV≈1%)に固定されることを示した。観察は拍動中の単一サルコメア長波形から得た。高速度サルコメア長計測(500 fps、3 nm級)と再帰定量化・リアプノフ解析により、正の最大リアプノフ指数と擬似データに対する有意差を確認し、偶然ではない決定論的カオスと結論した。私はこの秩序とゆらぎの共存を“Chaordic Homeodynamics(周期的カオス恒常性)”と提唱する。隣接サルコメア間の自発的位相ずれは細胞レベルの張力立ち上がりを平滑化し、出力の安定化に寄与する。本成果は、心筋のロバスト性と適応性を両立させる新たな恒常性原理であり、不整脈予兆の指標や人工心筋設計に資する。また、生体が微小なゆらぎを資源として用いる戦略を定量的に示した。 |
|
服部 祐季 名古屋大学 |
発達期における脳内マクロファージの細胞動態と機能脳や脊髄などの中枢神経系は、神経系の細胞だけでなく、血管系や免疫系に属する細胞など、さまざまな細胞から構成されている。これらの多様な細胞が複雑かつ動的に相互作用することで、脳の高度な機能が正確に維持されている。本研究では、その中でも免疫系に属する脳内マクロファージ「ミクログリア」に焦点を当てている。ミクログリアは脳内環境の恒常性を保つために不可欠な細胞であり、不要な細胞の除去、神経回路の形成、炎症応答の制御など、多岐にわたる機能を担っている。近年、シングルセル遺伝子発現解析の発展により、ミクログリアが一様な集団ではなく、遺伝子発現の違いに基づく多様なサブタイプから構成されていることが明らかになってきた。しかし、この多様性がどのような発生過程を経て形成されるのかは、依然として明らかではない。本発表では、マウス胎仔脳を対象とした生体イメージング、組織微細構造解析、細胞運命追跡解析、一細胞遺伝子発現解析など、複数の手法を組み合わせて明らかにしてきた、発達期脳におけるミクログリアの脳定着プロセスと多様性獲得メカニズムへのアプローチを紹介する。 |
|
辻河 高陽 名古屋大学 |
大規模疾患研究のためのハイスループット・ロングリード解析基盤構築ロングリードシーケンスは、構造変異、リピート伸長、およびエピジェネティック修飾を高精度に検出できる技術であり、希少・難治性疾患ゲノムの新たな理解をもたらしている。我々は1,000例を超える大規模ロングリード解析を実現するため、2台のPacBio Revioを中核としたハイスループットプラットフォームを構築した。本システムはロングリード全ゲノム解析および全長トランスクリプトーム解析を行うことができ、メチル化解析に必要なポリメラーゼ動態情報をBAMファイルに保持する解析パイプラインを備えている。全長トランスクリプトーム解析にはMAS-Iso-Seqを用い、すべての計算ワークフローはSingularityによるコンテナ化を行い、大容量メモリを有する複数のGPUサーバーから構成される高性能計算クラスター上で実行される。インフラストラクチャはスケーラブルかつセキュアなストレージと一元的なデータ管理機構を備えている。本プラットフォームは1ゲノムあたり最大150 Gb、1 MAS-Iso-Seqサンプルあたり最大160 Gbのデータ出力を達成し、難処理サンプルからでも高感度に変異やアイソフォームを検出することが可能となった。メチル化解析ではアレル特異的な遺伝子サイレンシングや体細胞モザイク性リピート伸長を同定し、包括的なトランスクリプトーム解析では神経疾患におけるスプライシング異常を明らかにした。すべてのデータは専用システム内に安全に保管され、インフラの発展に伴う堅牢なデータ保全と管理を実現している。我々が構築した統合型ロングリードオミクスプラットフォームにより、希少・難治性疾患の大規模研究において、先進的なゲノムおよびトランスクリプトーム解析が可能となった。 |
|
渥美 範俊 株式会社豊田中央研究所 |
脳有限要素モデルを用いた軸索ひずみに基づく外傷性脳損傷予測交通事故やスポーツ等における軽度外傷性脳損傷(mTBI、いわゆる脳震盪を含む)のメカニズム解明は、脳傷害基準の策定や頭部保護デバイスの開発において重要である。 mTBIは頭部の回転加速度による脳変形に起因すると考えられているが、脳組織や神経軸索の局所変形と臨床症状との関連を含む詳細なメカニズムは未だ明らかではない。本研究では、頭部衝撃時の神経軸索の変形を予測するため、群平均トラクトグラフィーから抽出した軸索線維束を明示的に組み込んだ脳有限要素(FE)モデルを提案する。モデルを実際のmTBI受傷事例の再現シミュレーションに適用し、神経経路毎の傷害値を解析した結果について紹介する。 |
|
市川 俊輔 三重大学 |
不安・抑うつに関わる腸内細菌の機能本研究では、腸内菌叢と精神健康(特に不安と抑うつ)の関連性を調査した。CES-D尺度を用いて17名の参加者を対照群と抑うつ群に分類した。腸内菌叢解析により、抑うつ群で特有の細菌種と代謝機能を検出することができ、精神疾患における腸内微生物叢の関与が示唆された。本知見は、腸内菌叢が気分障害に及ぼす潜在的影響を強調するとともに、精神的健康を支えるための腸内菌叢を標的とした治療介入の可能性を示唆している。 |
|
仲吉 朝希 名城大学 |
薬物代謝酵素に薬物はどのように結合するか: 分子シミュレーションに基づく解析さまざまな疾患に対する予防や治療の観点から、我々の生活と薬剤とは密接な関連がある。 生体内に取り込まれた薬剤は薬物代謝酵素によって代謝・分解され、排出される。薬物代謝反応の速度には個人差があり、これは薬剤投与時の薬効や副作用の発現の個人差に直結する。しかし、薬剤がどのように薬物代謝酵素に結合してどのように認識されるのかについて、原子・分子レベルでは解明されていないことも多い。我々は分子シミュレーションによって、薬剤がどのように認識するかを解明し、個別化医療の実現や薬効の高い薬剤の設計を目指している。本発表では、薬物代謝酵素と薬剤の複合体構造のモデリングや両者間の相互作用の解析について、最近の研究成果を紹介する。 |
|
宇佐見 享嗣 名古屋大学 |
昆虫を生きた工場として活用したモノづくり現在、我々の身の回りに存在する機能性分子の多くは、フラスコ内生産、つまり化学合成が常識であり様々な反応や触媒が開発・利用されています。しかし、位置立体選択性や官能基特異性が求められる分子の合成には多段階化に伴うコストと廃棄物問題が深刻となり、喫緊の課題として新たな反応や反応システムの開発が依然として強く求められています。一方、生体触媒(酵素)による高選択的な化学反応は、生合成や異物代謝分野で独自に発展・進化してきており、これら生物機能は有機合成化学とは異なる分野として捉えられ、積極的な利用が立ち遅れています。本発表では、最近得られた知見を紹介し、資源循環型モノづくりへの実現可能性について議論したい。 |
|
田中 良弥 名古屋大学 |
群れ形成への介入による昆虫制御『群れ』の形成は、動物に広く見られる重要な生存戦略であり、その理解は生物学的意義にとどまらず、害虫制御など実学的な応用にもつながる可能性がある。動物が群れを形成することには、摂食効率の向上や捕食者の回避といった利点がある一方で、個体間競争の増加や疫病の蔓延といったリスクも伴う。そのため、動物は生活史や生息環境に応じて、群れを作るか否かを柔軟に切り替えていると考えられる。 実際、近縁な種間であっても群れる種と群れない種が存在することが、さまざまな動物で知られており、群れ行動が種分化の過程で進化してきたことが示唆される。私たちのこれまでの研究から、ショウジョウバエと呼ばれるハエ目昆虫の中にも、盛んに群れる種とほとんど群れを形成しない種が存在することを発見した。さらに、神経生物学研究のモデル種であるキイロショウジョウバエを用いて、群れ形成を制御する脳内の神経細胞を特定しつつある。本発表では、昆虫の群れ形成を支える神経機構と、その理解を通じた害虫制御への応用可能性について議論したい。 |
|
蘇馬赋 名古屋大学 |
蚊の体内時計を標的にして聴覚機能と行動を阻害するBillions of people worldwide are at risk of diseases spread by Aedes aegypti mosquitoes. Disease control programs which rely on insecticide application are coming under increasing pressure due to rising insecticidal resistance. The development of novel control tools with new targets is necessary but requires a better understanding of basic mosquito biology. Aedes aegypti courtship takes place in aggregations (‘swarms’) which form only at certain times of day. Within swarms, male mosquitoes rely on hearing to identify conspecific females by listening for their sexually dimorphic flight sounds. Both the clock and hearing can thus influence mosquito copulation success. Research in other species has found that the clock can directly influence hearing function, suggesting direct links between the clock and hearing. Disruption of clock function could interfere with hearing, and therefore courtship, behaviors. Working with collaborators in Japan, Taiwan and the USA, I explore the connections linking the clock, hearing and courtship to explore novel pathways to generate new methods of mosquito control. |
|
萩尾 華子 名古屋大学 |
魚の高次視覚機能の解明とウナギ仔魚の餌開発を目指して効率の良い漁業と養殖業に貢献するため、神経科学的アプローチにより魚の視覚を明らかにし、ウナギの仔魚(孵化後初期の魚)の餌開発も目指す。これまで私たちは魚の視覚回路や視覚機能を調べたところ、哺乳類と類似した高次視覚系をもつことを明らかにした。高度な視覚認知能力をもつとされる魚種の視覚回路や視覚機能もフランスCNRS研究所との国際共同研究などにより明らかになりつつある。また、ウナギ仔魚の成長に伴う味覚器の発達や摂食により活動した脳領域もわかった。さらに、成長促進物質を添加した餌を別魚種の仔魚へ給餌する実験を進めており、魚の高成長を目指す。 |
|
Raquel Costa 名古屋大学 |
人間と動物のミスコミュニケーション、安全な相互作用に対するリスクをもたらすのか?During close encounters between humans and animals, each species relies on its own communicative signals. However, same signals can carry different meanings across species. This is true even when comparing humans and non-human primates, which are closely related in evolutionary terms. When humans anthropomorphize primate behavior—interpreting their expressions through a human emotional lens—they may unintentionally display signals that primates perceive as threatening or intrusive. Our research indicates that humans are strongly motivated to interact with primates. Yet, close proximity not only increases aggression from the animals but also raises the risk of disease transmission. To mitigate these interactions, we need to examine the signals exchanged between different species, and how these are shaped by human cultures. Collaborating with researchers in Japan and the United States, we ought to build a more culturally and biologically informed approach to the study of human-animal interactions. |
|
Bellegarde Fanny 名古屋大学 |
栄養ストレスに対する植物の適応メカニズムの解明Between soil impoverishment and global warming, the instability of agricultural yields is constantly increasing. It is now crucial to develop less polluting and more sustainable agricultural methods by improving our understanding of the natural adaptation of plants to their environment. Plants can remember some environmental stresses. Nitrogen nutrition is a major environmental factor that regulates the growth and productivity of crops, but it is unclear whether plants remember nutritional stress. My results strongly suggest that plants can remember nitrogen deficiency stress and react. Understand its mechanisms will permit to imprint the memory, during seedling production process, to create seedlings with both high yield and stress tolerance. |
|
宮武 広直 名古屋大学 |
高赤方偏移宇宙論の開拓Recent advancements in astronomical observational technologies have revealed that most of the energy density of the Universe consists of unknown components, i.e., dark matter and dark energy. Dark matter plays an essential role in forming stars and galaxies through its gravity, while dark energy accelerates the expansion of the Universe. It is of great importance to investigate the nature of dark matter and dark energy. In the 2010s, wide-area astronomical imaging and spectroscopic galaxy surveys enabled us to conduct cosmological studies with large-scale structure of the Universe. Large-scale structure is sensitive to the nature of dark matter and dark energy since the structure of the Universe evolved under the two competing effects: the attractive force (gravity) by dark matter and accelerating expansion caused by dark energy. It turned out that the clumpiness of the structure at present measured by those galaxy surveys is likely smaller than that predicted from the measurements of the cosmic microwave background (CMB). However, the significance of the difference is not high enough, and the large-scale structure measurements are confined to z<~1, and thus it is necessary to investigate large-scale structure at high redshifts. To this end, we have started a project to conduct high-redshift large-scale structure cosmology. In this poster, we will explain our ongoing project that uses galaxies at z~4 as a tracer of large-scale structure, as well as a future observational campaign being developed with internatio. |
|
早川 尚志 名古屋大学 |
1956年2月の激甚太陽粒子嵐の復元太陽の活動が活発になると、荷電粒子が高エネルギーに加速される場合がある。このような太陽高エネルギー粒子(SEP)は、太陽と地球の相対的な位置関係次第では地球に到達することもある。SEPは十分にフラックスが多く、スペクトルも硬いと地表面で宇宙線量を増やすほどに発達することもある。このような現象をGround Level Enhacement (GLE)という。1956年2月23日のGLE5はこのようなGLEの中でも最もスペクトルが硬く、フラックスも大きく、宇宙天気災害の評価のベンチマークとして活用されて来た。一方、その大元のデータについては不明な点が少なくない。そもそも原典史料がどこに行ったかを把握している科学者もほとんどいないのが実情であった。弊チームは近年その原典史料のほとんどを再発掘し、フルエンスの最大量、スペクトルの硬さ、およびその時間的変化の復元を大幅に改訂した。弊チームの結果では、GLE5は先行研究に比してそのスペクトルをやや軟化させ、最大フルエンスが10%を増加させた。この研究成果は当該GLEの大元のデータを大幅に改訂し、時系列精度を向上させ、スペクトルに関するさらなる議論の基礎となることが期待される。 |
|
李 乃琦 名古屋大学 |
「言語のシルクロード」を復元古代のシルクロードは、物資や宗教だけでなく、言語と文字の交流によっても支えられていた。本発表では、7世紀から13世紀にかけて東アジア各地で編まれた20種類の仏典辞書(音義)を中心に、サンスクリット語・漢語・日本語など多言語の交錯から生まれた「言語のシルクロード」の実像を復元する試みを紹介する。これらの辞書は単なる語釈書ではなく、異文化理解と翻訳の知の結晶であり、その研究は東西の知識体系をつなぐ鍵となる。本発表では、現在進めている「古代仏教辞典データベース」の構築と分析を通じて、古代の人々がいかに外国語を理解し、自国語へと取り入れていったのかを明らかにし、人文学と情報学を架橋する新たな視座を提示する。 |
|
宮尾 亮甫 南山大学 |
気候変動に対する都市法の寄与に関する分析気候変動は、特定の地域の問題ではなく、人類共通の課題となっている。気温上昇のみならず、年間降水量の変動やゲリラ豪雨など異常気象の頻発・強度の増加が堅調である。とりわけ、激甚化する水害への「適応」策は、都市の存続に直結する喫緊の課題となっている。(日本)政府も近年、「流域治水」という考え方を掲げ、河川管理者だけでなく、流域住民・自治体・企業が協働し、氾濫の防止から被害軽減、早期復旧に至るまで多層的に取り組む方向を示した。その実現に向け、都市河川浸水被害対策法の改正により雨水貯留機能保全域や雨水貯留施設の整備促進などが導入された。 しかし、日本の都市計画法体系では、こうした気候変動「適応」策が都市計画に十分に組み込まれていない。気候変動適応法は自治体に地域計画の策定を促すが、都市計画法や建築基準法との連動は弱く、気候変動対策や脱炭素は実際の土地利用や開発行為及びその許可の判断に反映されにくい。また、雨水貯留浸透施設の設置や緑化などは、一部の自治体での条例を除いて、義務付けられていない。 本研究では、伝統的な法律学の研究方法である比較法研究の手法を用いて、ドイツの都市法制を参照し、日本法への示唆を得ることを目的とする。 ドイツの建設法典(日本の都市計画法に相当)では、土地利用計画において気候保護及び気候変動への適応を考慮する義務が明記された。さらに、緑地帯の指定、不浸透水面の制限、雨水貯留施設や再エネ設備の配置などを都市計画うえで具体的に規定できる法制度設計になっている。このように、ドイツの都市法制度では、都市空間における気候変動適応が制度として埋め込まれている。 本研究は、ドイツの都市法制度の特徴を明らかにし、気候変動適応と都市計画との整合を義務付けることの必要性といった示唆を得る。比較法的アプローチにより、環境・防災・都市計画を横断的に再構成し、気候変動に耐え得る都市法を創造することが本研究の目指す方向である。 |
|
王 家元 東海東京証券株式会社 |
大学における起業家教育と起業意欲の関係大学は経済成長において重要な役割を果たしている。有能な人材を供給するだけでなく、研究部門が集中しているため、イノベーションの重要な源泉としても機能している。しかし、研究の成果が自発的に経済成長に結びつくわけではない。大学は、一連の起業家活動を通じて、研究成果の実用化を加速させる努力を行う必要がある。これには、研究者や学生に対する起業家教育も含まれる。本稿では、2021 年の横断面データを用いて起業家教育プログラムのTongali Project が学生の起業意向との関係を分析する。その結果、大学の取り組みが効果的で あることに一定的に示された。 |